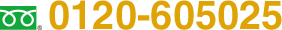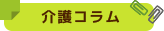
老人ホームへの入居を迷っているご家族へ。入居するメリット
2021年09月01日
- 家族の介護
- グループホーム
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム

自宅での介護はとても大変だけれど、両親や祖父母を老人ホームに入居させるのはためらう――そう感じるご家族は多いのではないでしょうか。今回は老人ホーム入居についてのお悩みをとりあげ、その解決事例をご紹介します。
家族が老人ホームの入居を迷う理由
家族が老人ホームへの入居を迷う理由はさまざまですが、よく聞かれるのは、以下の3つです。
(1)家族が介護しなければ、という義務感
今まで良い親子関係・嫁姑関係を築いてきた家族ほど、「今まで育ててくれた」「良くしてくれた」という思いが強く、「今度は自分が面倒をみなければ」と考えます。自分の親や義理の親を老人ホームに入居させることは、家族としての義務を放棄したことになるのではないかと後ろめたさを持つご家族は多いのです。
(2)親族からの目が気になる
世間にはいまだに介護=女性がするもの、という考え方があります。そして実際に介護を担うのは、実の娘や、お嫁さんが圧倒的に多いのが現実です。そこにもし親族から「家にいるのが一番」「家族に見てもらえて幸せ」等の声があれば、親族からどう思われるかを気にして、入居を言い出せなくなってしまいます。
(3)自分が介護したほうが良いケアができる
例えば「ホームには多くの入居者がいるから、一人ひとりに十分なケアができないのではないか」と考える方もいます。在宅介護を頑張っている方ほど、本人のことをよく分かっているという想いから「自分が介護したほうが良いケアができる」「自分にしかできない」という思いをもっており、入居に抵抗を感じてしまうのです。
老人ホーム入居を決めたAさんのケース
仕事を続けながら同居の母親の介護も頑張るAさん(女性)も、まさにこうした状況にありました。親子関係は良好で自宅での介護歴も長く、親族もこのままずっと自宅での生活が続くものと考えていました。しかし、徐々に母親に認知症の症状が現れ始め、介護負担が増加。思うような介護ができなくなっていました。その様子をみかねたケアマネジャーが地域の「介護者の集い」にAさんを誘いました。
Aさんはそこで自分と同じような境遇、悩みを他の人も抱えていることを初めて知り、自身も素直な感情を吐露することができました。また「良い娘のままでいられるかどうかは入居後の関わり方しだい」という参加者の言葉を聞き、入居の話を母親にすることを決意しました。母親もAさんに負担がかかっていることを理解しており、入居が決まりました。
入居後、Aさんは、自身の生活(仕事等)と親の介護への関わり方に区別がついたことでストレスを大きく軽減できました。精神的な余裕ができ、逆に入居前よりも母親に関わる時間が増えたそうです。母親のほうも環境が変わったことによる認知症の悪化はほとんどみられませんでした。ホームの環境に慣れてからはレクリエーションに積極的に参加したり、仲の良い友人を作ったりして寂しさを感じることもあまりなくなったということでした。
入居について迷うよりも、入居後の「家族の関わり方」を考えよう
自宅での介護は本人のペースで過ごせるという利点はありますが、どうしても介護の手が不足がちになります。それに比べると、老人ホームの介護には以下のような利点があります。
・ホームでは栄養バランスを考えた食事が提供されるため、栄養不足の心配をしなくて良い
・空調管理されているため、夏の脱水や冬の暖房事故の心配が少ない
・家族では見落としがちな病気の兆候を早く発見してくれる
・日中や夜間に急変しても適切に対応してくれる
・日課があるため、本人の生活にメリハリをもたせることができる
・専門家による適切な介護・認知症ケアにより、本人の周辺症状が落ち着き、穏やかに過ごせる
家族といっても、介護を長く続けるには多大な負担がかかります。子育てと違い、先が見えない介護に対しては、家族がどこまで関わり、どこから他者(介護サービス等)に任せるのかを考えることは自分たちの生活を保つために大事なことです。介護サービスを受けることに後ろめたさを感じる必要はありません。
Aさんのように入居後家族への関わりが多いことは、ご本人にとっても、老人ホーム側にとっても大きなメリットです。本人の情報が少ない入居直後は、家族から入居者の生活歴や趣味、自宅でどのような介護をしてきたか、といった情報を得ることで、個別ケアが深まります。
自宅での介護でも、介護サービスの利用方法によって家族の負担感が違ってきますが、老人ホームもどのように利用するか、という視点は重要になるでしょう。負担感に押しつぶされてしまう前に老人ホームへの入居に踏み切る。そして入居後に出来る範囲で積極的に関わる。こうした視点を持っていれば、より良い関係は継続できるのではないでしょうか。
ニチイ学館では有料老人ホーム・グループホーム等の居住系介護サービスを提供しております。
関連情報