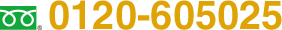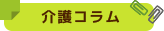
全国に600カ所、最近増えてきた「認知症カフェ」とは?
2016年06月29日
- 健康と生活
- グループホーム
- 認知症
- 認知症カフェ

あなたは「認知症カフェ」を知っていますか? 認知症カフェは、「認知症の人の介護者の負担を軽減するため、認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う」ことを目的に、政府によって設置が推進されています。
今回は、認知症カフェが具体的にどのような場所で、そこに参加することによって、どのようなメリットを受けられるのかを紹介します。
「認知症カフェ」とは?
政府発表によれば、現在、日本の高齢者の約4人に1人が認知症、またはその予備群といわれています。そして、2025年には、認知症患者が700万人を超えると見込まれています。
そのような背景のもと、厚生労働省を中心に、認知症の人が自分らしく暮らしていける社会をつくる「新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)」が策定されました。その中に「認知症の人の介護者への支援」という大きな柱があります。認知症患者本人だけでなく、介護者の支援にも力を入れ、介護者の負担を減らす努力をするということです。そして、介護者支援の一環として「認知症カフェ」があります。
それでは、認知症カフェでは具体的にどのようなことをするのでしょうか?
「認知症カフェ」ではなにをするの?
認知症カフェは、自治体やNPO法人などさまざまな運営母体があります。ここではニチイの認知症カフェ(※)を例として紹介します。
※グループホーム拠点を中心に、自治体の認知症施策実施状況に合わせて拡大中です。未実施のエリアがあります。
参加者は、認知症患者本人とその家族、地域のボランティアの方々。対応するのは、認知症介護実践者研修を修了した専門スタッフです。参加人数5~10人に対し、2~3人のスタッフで対応します。開催頻度は月1回で、1時間半から2時間程度を標準としています。参加費用は、飲食代の実費程度です。
参加者は自己紹介をしたあと、茶話会として他の認知症患者やその家族と情報共有をしたり、ボランティアによる演奏会などで楽しく時間を過ごしたりします。
専門家による認知症に関するミニ講義も催されます。テーマは「認知症の基礎知識」「認知症の高齢者のケアポイント」「介護保険の賢い利用方法」など、家庭の介護ですぐに役立つ内容です。講義とあわせ、専門家に直接、介護に関する悩みを相談することもできます。
「認知症カフェ」に参加するメリットとは?
認知症カフェに参加することで、患者本人は、社会的なつながりや役割を得て、イキイキと楽しい時間を過ごすことができます。介護を担う家族同士は、お互いの介護に関する体験談や情報交換をし、悩みを共有することができます。それが息抜きとなり、介護者の精神的、身体的な負担を軽減します。
また、専門性の高い介護のプロと直接出会える場なので、介護サービスなどの情報を気軽に得る機会となります。
さらに、介護関係者だけでなく、同じ地域に住む人のボランティアとのつながりを持つことによって、認知症への理解が進むことが期待できます。
地域の認知症カフェにお気軽に参加してはいかがでしょうか。
関連情報
関連サービス